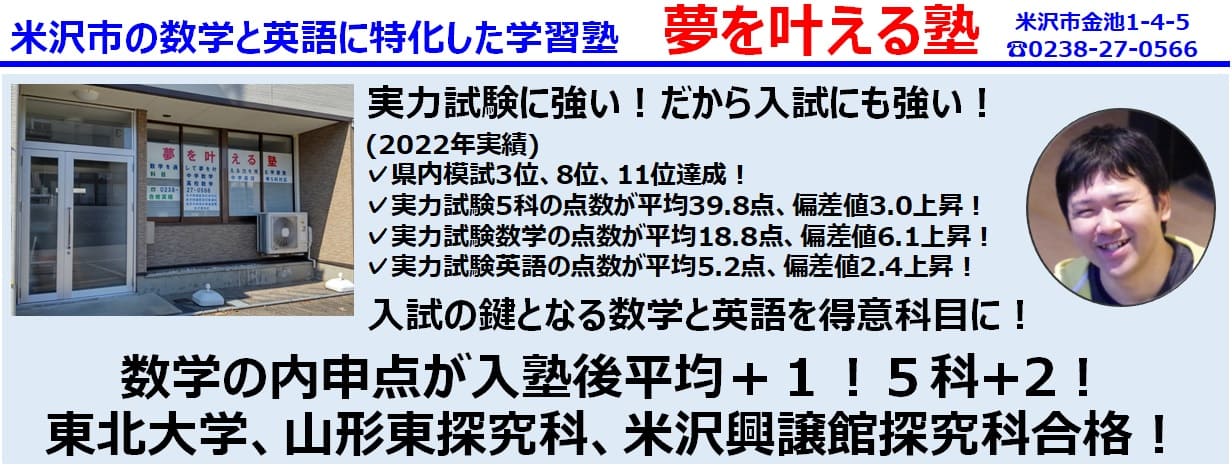
中学2年生男子の生徒様とのやりとりです。
ボクからの厳しい指導によく応えてくれています。
頑張ろうとしている分、打てば響くので、つい厳しくなってしまうのかもしれません。
なお、本投稿は「厳しさについて」というような話ではありません。
漢字の問題に正解するために
生徒様は自学で漢字を練習する事にしました。
今回の生徒様以外にも、漢字を頑張って自学ノートに埋めてくれる生徒様は多いです。
毎回疑問に思ってしまいます。
「それで覚えるの?」
「それが漢字を覚える上で最も良い効率の勉強方法なの?」
と・・・。
実際にノートに何度も書いた後に試験をしても、あまり正答率は良くないです。
過去、色々な生徒様に聞いてきました。

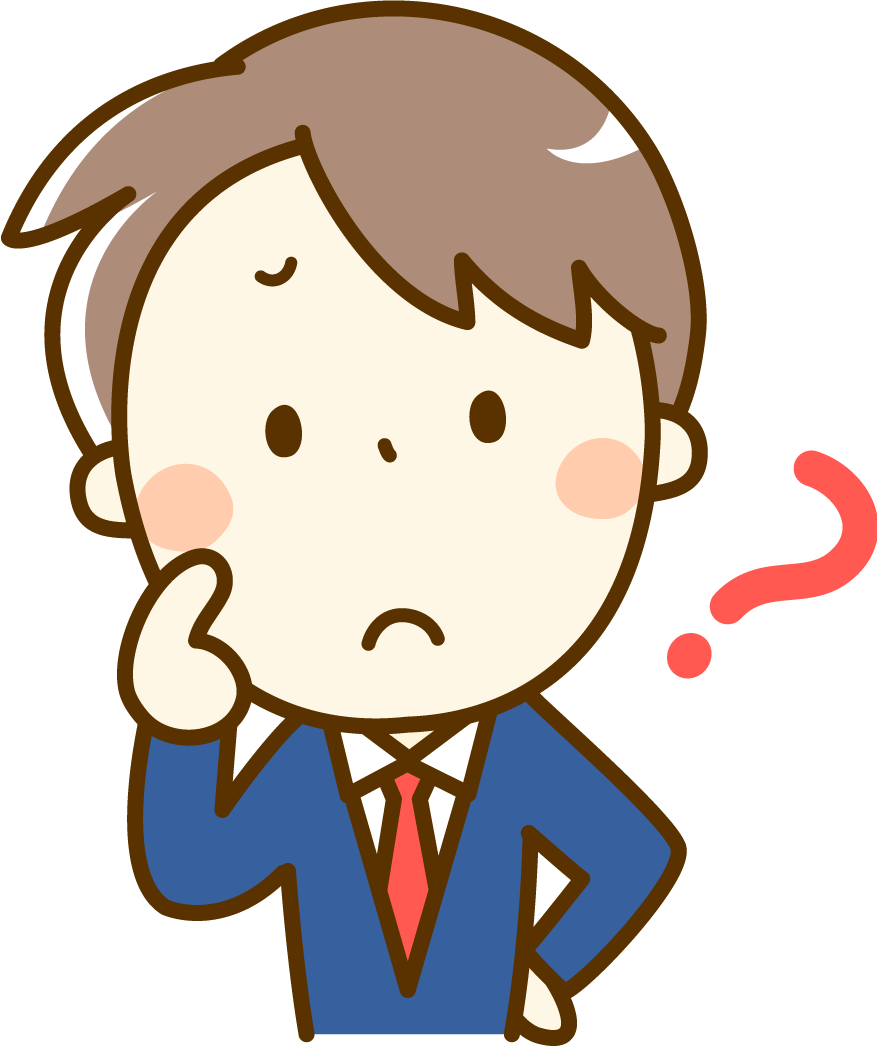

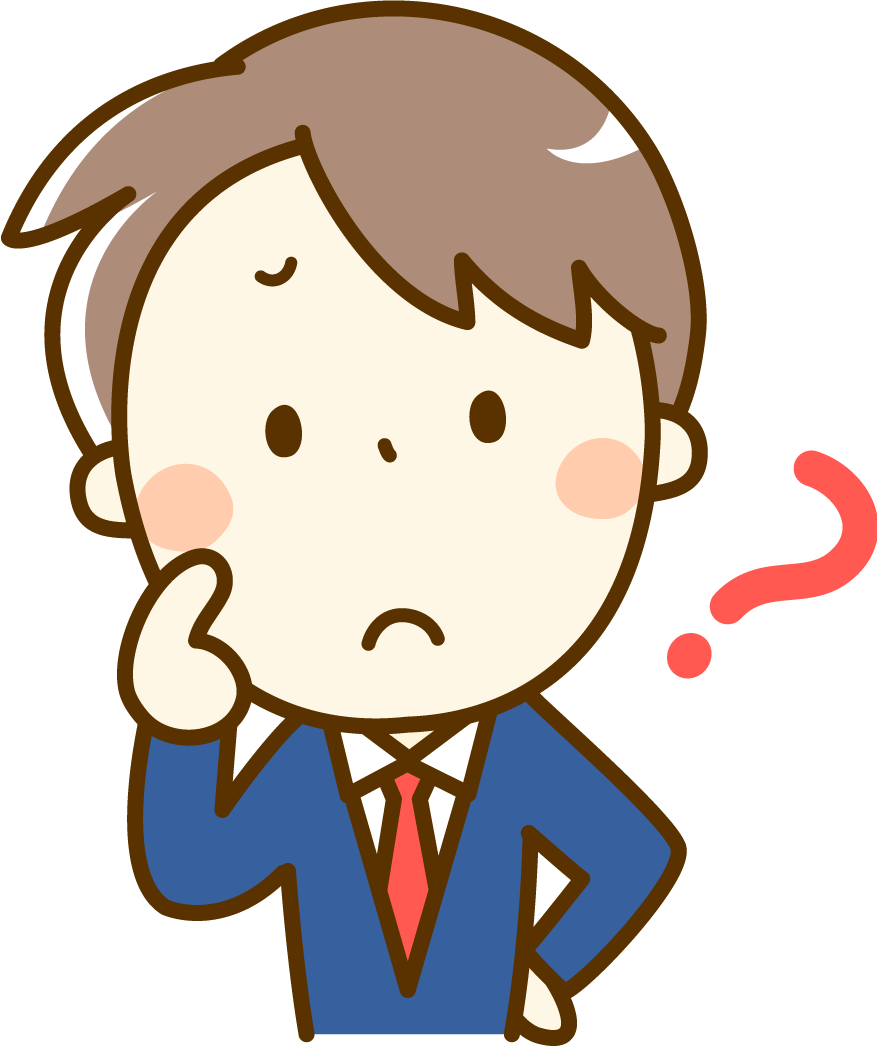
自学、負担にしかなってないです。
自学が役に立っているという様子、ほぼありません。
「埋めるための勉強をする」という形式的なものになってしまいます。
「作業」になりがちです。
内申点がもともと上位の生徒様は自学が無くても勉強しています。
そしてその勉強方法はノートを埋めるという作業ではありません。
自学は効率の良い勉強時間を減らすものになってしまっています。
内申点があまりよくない方は自学に時間をとられ、本来やるべき勉強ができていません。
自学でがんばってノートを埋めておられます・・・。
それが中々成果に結びつかないので、負のスパイラルです。
内申点に影響するので、出されてしまったらやるしかない。
この指導方法は早く止めた方が良いですよ!
・・・話がそれてほとんど進んでいません。
今回は漢字練習後に問題を出して確認をしたときの話です。
「扱」と「怪」
漢字の読みを言い、その漢字を答えるという問題に答えてもらいます。
何問目かで「扱う」を漢字で書く問題を出しました。
生徒様:うーん。
那須:「扱う」って何で扱うのかな?足?口?
生徒様:手ですね。
那須:そう!つまり、手偏だ!
生徒様:あっ!
見事正解にたどり着きました。
次に「怪しい」を漢字で書く問題を出しました。
生徒様:うーん。
那須:同じ話で「怪しむ」のは何?
生徒様:うーん。
那須:手?口?
生徒様:あ、頭?
那須:おぉ。
生徒様:頭・・・
那須:うん、もうちょっと言うと、頭の中だね?
生徒様:「心」・・・
那須:それも心なんだけど、もう1つ心を表す漢字についてる部首があるね?
(忄を書く)
生徒様:りっし・・りっしんべん?
那須:そう!
那須:後は音で、「怪しい」の漢字は別の読み方は何?
那須:怪しい話することなんて言う?
生徒様:(あっカイダン?ということは・・・)カイ?
那須:そう!
生徒様:あっ!
見事正解にたどり着きました。
部首
部首にどんな意味合いがあるのか考えながら覚え、思い出すと良いでしょう。
手でするものは手偏、心の動きはりっしんべんです。
移動であれば行人偏、体の部位であれば肉月、神や祭りに関する示編等々・・・。
これがわかるだけで漢字の大まかな形が想像できます。
必ずしも頭に思い描いたイメージと漢字の部首が一致するわけでもないので、そこは注意です。
音
漢字には音読みがあります。
音読みにはその音にするための要素が漢字の中にあることが多いですね。
今回であれば、「怪しい」の「カイ」ですが、「半径」や「経営」等の「ケイ」という読みに似ています。
これは「圣」という部分が「ケイ」や「カイ」の音を出させるためのものだと考えます。
心に関するもので「カイ」と読む漢字。
それが「怪しい」です。
思い出す方法
ここまででわかることは「覚えているけど思い出せない」です。
「漢字練習をしたから覚えたのだ」と言われると否定はできません。
一方で、覚える事だけではなく、思い出すことを練習しないと、勉強としては不足ということもお分かりいただけると思います。
「漢字は何回書いたら問題に答えることができるのか?」
何回書いて覚えようと、思い出せなければ得点にはなりません。
書く回数よりも、思い出せるかどうかを何回もチェックするようにしましょう。
「部首」や「音」は思い出すための手掛かりとなりやすいので利用するといいです。
その前提として、音を聞いたらその音を持つ漢字がいくつも浮かんでくる必要があります。
一朝一夕で漢字を書けるようになるわけではありません。
小学生からコツコツと漢字の勉強をしっかりやってくれば、正解するのもそれほど難しくありません。
※ちょっと特殊な漢字は難しいと思いますが・・・。
これは漢字だけではありません。
中学生からコツコツと勉強したかは、大人になってからの能力が違ってくると思いませんか?

