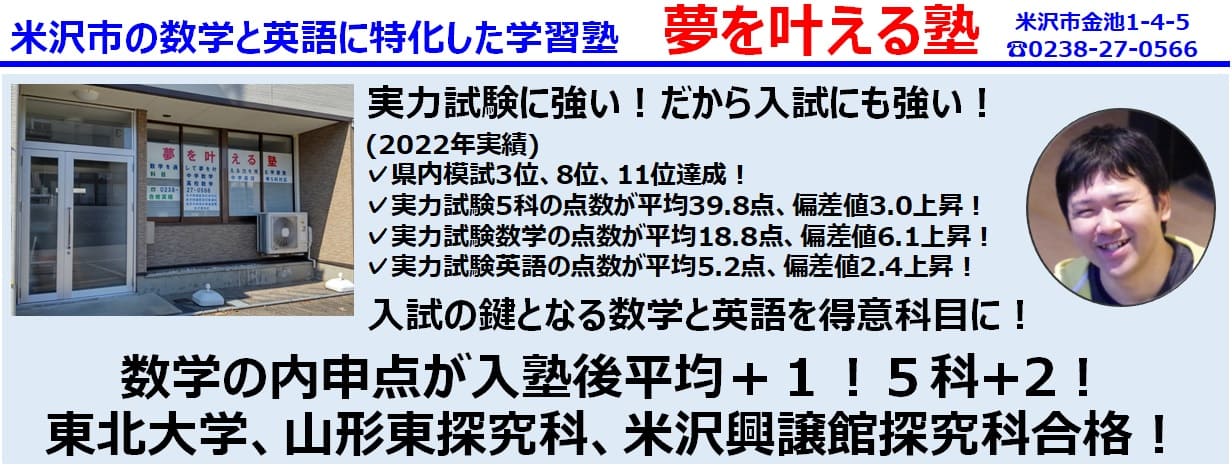
中学2年生女子の生徒様とのやりとりです。
かなり謎なタイトルになりました。
古事記伝というオチ
古事記伝と言えば本居宣長さん。
「聞いたことあるけど何した人だっけ?」
と思われる方も多いのではないでしょうか?
タイトルにもあります通り、とりあえず古事記伝なんですけれども。
なんとなく、ぱっとしない印象ありませんか?
実は結構重要?
ボクの中では結構重要な人物だと思ってます。
社会の教科書に載るくらいですから、それはまあ重要な方なんですけれども。
「何が重要なの?」
って思いませんか?
本居宣長は教科書で
日本古来の精神に学ぼうとする国学がおこり、本居宣長が古事記伝を書いて国学を完成させた。
こんな感じで説明されています。
古事記伝と国学・・・。
「金剛力士像」とか「関ケ原の戦い」等と比べるとなんとなくインパクトに欠ける気がします。
でもボクは次のような見方をしています。
※教科書+その他見聞したものであり、専門的に学んだ訳ではありません。
古事記伝は日本の神話である古事記をもとに作られている。
古事記ではイザナギやイザナミといった神々が日本を作り、その子孫が天皇であるとされる。
古事記伝から日本の神話を知ることにより、「日本は天皇のものである」ということから、天皇を尊ぶ事となる。
宗教的な感覚は現代の日本人には少し遠い世界のように感じるかもしれません。
しかし、宗教の信仰は日本以外では根強く存在しているという事も、他人事として感じているのではないでしょうか。
そう考えるとこの日本神話は当時の仏教や儒教などととって変わる信仰の対象になると思いませんか?
※現代の私たちは平和信仰とでも言いましょうか
これによってその時代に批判的な考えや天皇を尊ぶ考えに繋がり、尊王攘夷に影響を与える事になります。
教科書でもそんな説明がされていますね。
尊王攘夷
ボクの日本の歴史の感覚としては、この尊王攘夷は結構大きい出来事なんですね。
大化の改新に始まる日本の歴史は仏教で国を治めるところから始まります。
政治の中心は天皇にあり、天皇が日本の神話である古事記(国内向け)と日本書紀(国外向け)を作成します。
※国内向けは「天皇こそ頂点」的なものであり、国外向けは「日本は天皇が支配している国です」とすることで日本を中国などから守る、という事なのかと思います。
やがて奈良時代に仏教の力が強まり過ぎて、それを平安時代に天皇に戻します。
そこから江戸時代よりも長い平安時代が天皇中心に動きます。
「荘園」が経済的な力となり、次第に武士が力をつけ、鎌倉時代で武士の時代になります。
途中後醍醐天皇が政権を獲得しますがすぐに室町幕府の武士の時代に戻ります。
そこから江戸時代終わりまで、武士です。
そして長かった武士の時代の終わりが尊王攘夷です。
再び明治維新によって天皇に政治が戻ります。
その尊王攘夷に一役買っているのが国学の本居宣長「古事記伝」です。
こうしてみると結構重要な役割になってませんか?
そもそも古事記と言うものは文学作品ではなく、万葉集のようなものとは一線を画すわけです。
四字熟語のインパクト?
那須:・・・(上記のようなお話を)・・・
那須:てわけでさ、結構重要な人でしょ?
生徒様:うんうん。
那須:本居宣長の国学は歴史が動いた要素あるよね?
那須:杉田玄白の解体新書とかの方が、なんか四字熟語でインパクトなんか強いけどさ?w
生徒様:w
ちなみに解体新書はこれはこれで重要な要素があります。
これ自体にというよりも、その背景ですね。
これは次回記事にしたいと思います。
そして記事を書いているときに気が付きました。
「古事記伝」
これも四字熟語じゃん!

