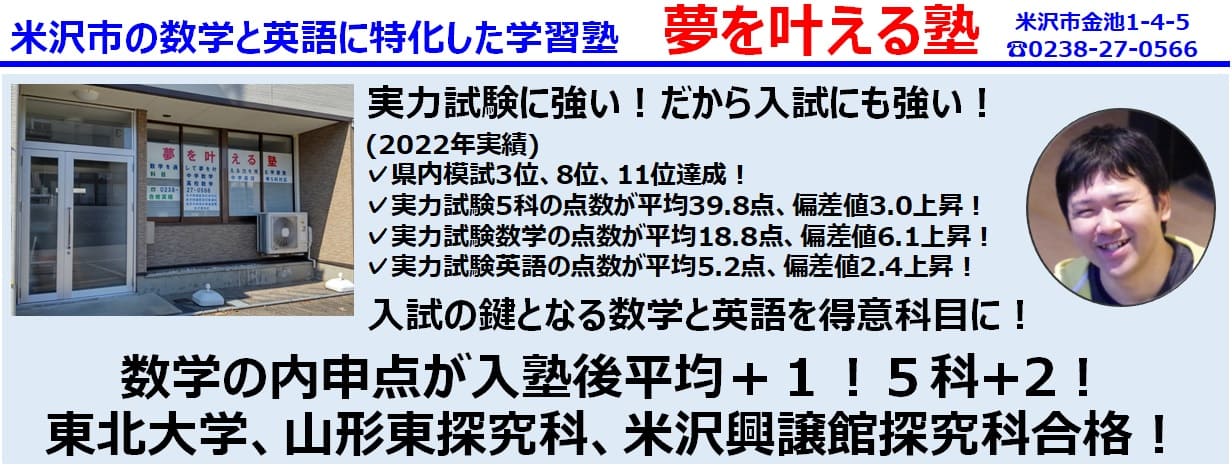
中学3年生女子の生徒様とのやりとりです。
この地層はどちらに傾いていますか?
理科で正答率の低い柱状図の問題です。
「この地層はどちらに傾いていますか?」以外にも、何パターンか解き方がわからないと解けないような問題があります。
問題は出せないので問題集などから探してみて欲しいのですが…。
A地点、B地点の標高とその地点の柱状図があり、それらの情報から地層の傾きを求める問題です。
どうやって解くか、わかりますか?
教科書を見ても、問題の解き方なんて書いていないんですよね。
教科書で学んだ知識だけでは、中々どう解いてよいかわかりません。
「それってどうなの?」とも思いますが、考えれば解けなくもない。
ただ、どちらかと言えば、問題集などに取り組んで、「ちゃんと解けるようになる努力をしたか」という意味合いの強い問題の様にも思います。
という事で、解き方がすぐにわかるような問題ではありません。
問題に対してどのようなアプローチをすれば解けるのか、生徒様と一度一緒に取り組む必要があるでしょう。
そのためには問題の絵を紙に移す等の準備が必要で、一緒に問題を解くための作業をすると、それなりに時間が掛かります。
この問題が必ず出るのかと言えば「そうとは限らない」です。
でも、そういう積み重ねが得点に繋がるわけですから、時間を惜しまず時間を使って一緒に取り組んで頂きます。
作業は結構楽しい
パズルのような感覚でできる作業なので、作業自体は楽しいと思います。
※ボクは楽しい
試験中などで時間に追われると、ちょっと焦りますけれども。
生徒様に絵を描いてもらって、実際に取り組んでもらいました。
無事答えにたどり着きましたね。
生徒様:(こうやって解くんだ~)
と言ったご様子でした。
・・・しかし、絵がうまい。
那須:(柱状図、超上手・・・)
と言いたくなる気持ちをぐっとこらえ・・・。

うまい絵に嫉妬した、負け惜しみ・・・ではありませんっ!
半分はそうなのですが、実際に時間のかかる作業です。
試験中にこれをやりだすと後半時間が足りなくなる可能性もあります。
理科は比較的時間があまりやすい科目です。
一度飛ばして後で解くという方法もおすすめです。
那須:これ、どうやって解くか、教科書じゃやらないよね。
生徒様:やらないですね。
那須:解き方が分かれば、時間かければ解きやすいんだけどね。
那須:正答率はめっちゃ低いね。
という事で、いったん問題に答える上で必要な分は作業できました。
生徒様から提案が・・・。
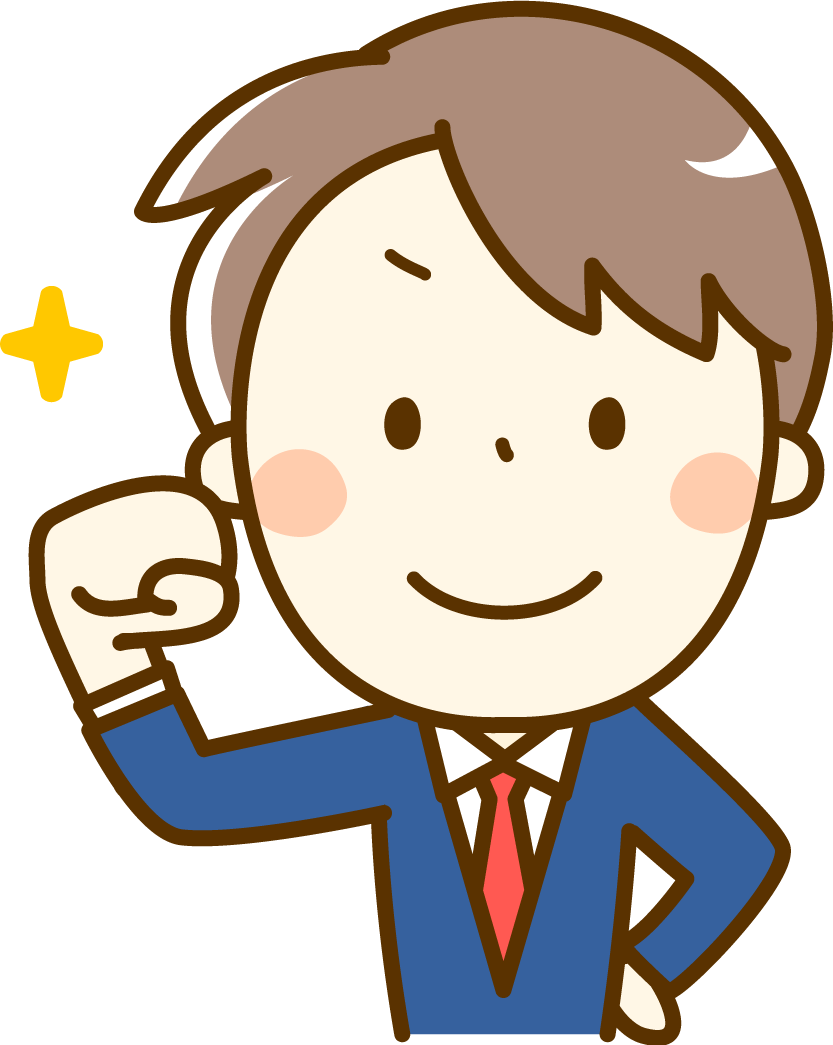
那須:もちろん!
こういう時、答えに関係ないけど続きをできるって、強いです。
理解しようとする気持ち。
生徒様からいつも感心させられます。
すごく無いですか?


