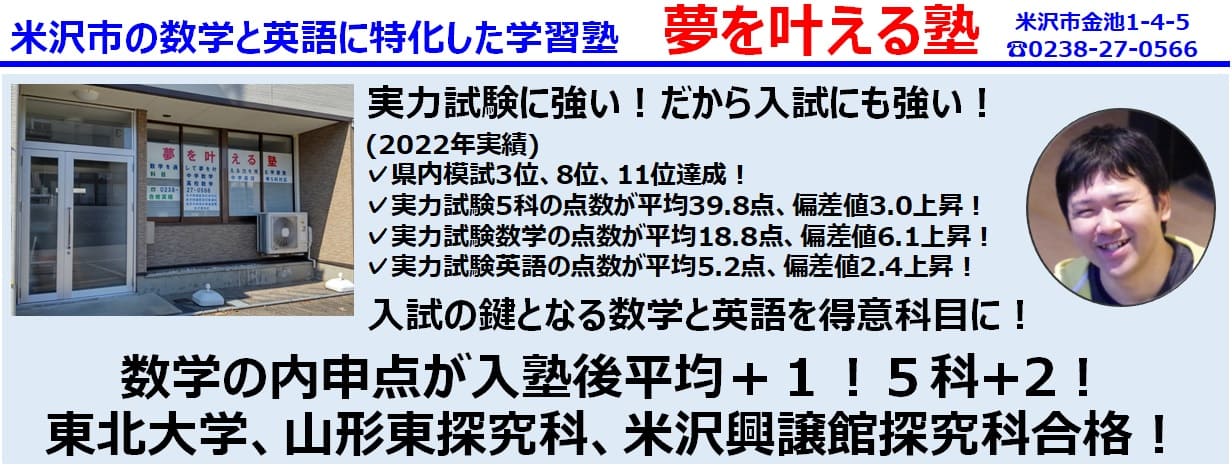

夏休みと言えば、問題集を解くような課題と共に、次のような課題が出ます。
- 絵を描く
- 調理記録
- 日記
- 自由研究
何をしていいのかわからず悩んでしまう方も多いのが自由研究です。
自由研究とは
「なんでもいいから実験したり作ったりする」
そんなイメージがあるかもしれません。
確かに興味のあるものや好きなものを探究する事は学びに繋がる部分もあります。
しかし、「課題になっているからやっただけ」の実験から得られる学びは少ないですね。
そもそも研究とは
「研究」は次のように説明されていました。
物事を学問的に深く考え、調べ、明らかにすること。また単に、調べること。
ただ、一般的には次の要素が付随します。
- 誰も知らないことを明らかにすること
少し表現は違うかもしれませんが、「無から有を生み出す事」です。
単に調べるだけを研究とあまり言いたくはありません。
それはただの勉強ですね。
決まりきった実験をするだけを研究と言いたくもありません。
それはただの作業ですね。
自分で新しいものを生み出して欲しいと思っています。
せっかくの夏休みなので勉強ではなく、一歩進んだ研究をしてもらいたいと思います。
ただ、「誰も知らない事」の確認は、小学生や中学生では難しいものがあります。
ですから、教科書や参考書の知識ではなく、自分で調べて何かを明らかに出来ればそれでいいのかなと思っております。
自由研究の参考題材
巷では自由研究の参考題材をまとめた書籍や、インターネット記事があります。
完全に悪い物とは言えませんが、学習のチャンスを奪っている気がしてなりません。
確かに何をしていいのかわからなくて困ってしまう子も多い事は事実です。
ですが、それは普段から好奇心を持って過ごすという事に意識改革するチャンスでもあります。
思う存分に困り、考え、悩み、それを解決してもらうことが学びではないかなと思っています。
参考題材を実験しただけの自由研究
やはりそういった参考題材から選んで実験した方の自由研究の内容は稚拙に見えてしまいます。
結果をまとめていても、いまいちその研究の本質をわかっていません。
自由研究の醍醐味は、実験結果から学ぶことではないと思っています。
まずは、「何を調べたいのかという題材の選定」が1つの重要な観点です。
そして、「それを調べる方法の考察」がもう1つの重要な観点です。
これらは参考題材となっているものを、ただなぞらえて実験しただけでは身に付きません。
そのような題材をそのまま実験するような事は時間の浪費になってしまいます。
結果が分かっていますから、ただの「作業の練習」です。
あまりおすすめできません。
考えるきっかけは与えても答えは出さない
生徒様から自由研究で何をしたらいいかをご質問頂きます。
「自分で考えなさい」とは言いませんが、「これをやってみたら」とも言いません。
興味のある分野を聞いてみたり、そこで疑問に思った事が無いか聞いてみたりします。
ある方は特定の生物に興味があり、その生物に外的な刺激を与え、その反応を研究して見たいと言っていました。
※道徳的にやって良い事と悪い事の分別は補足しますが
題材としては学校で学ぶ科目と関係性が低いのですが、自分で考えた研究ですから、学びのある研究になるはずです。
ある方は植物に興味があり、例えば発芽する条件を調べてみてはどうかという話になりました。
理科の問題でよく出題される「対照実験」という用語があります。
どのように条件を作ると実験としてふさわしいものになるのか、その意味が真に理解できると思います。
このような学びを奪ってしまうので「自由研究のお助け本」には肯定できません。
ただ、題材などが決まらないときに、身近に手を差し伸べてくれる存在があるのであれば、そのような本には頼らない方が良いと思います。
※手を差し伸べた結果が「自由研究の押し売り」であるかとが多いので困ってしまうのですが・・・。
余談ですが
私の自由研究は「山形県公立高校入試問題で出題された英語の問題に使われている英単語の調査と、それを考慮した英単語対策方法の立案」です。
どのような英単語が、どれくらい使われているか調べています。
5年間分約7500の英単語を全て集計し、対策を考えています。
試験に出るかもわからない英単語をただ学ぶより、効果がありそうだと思えませんか?
本当は生徒様にこのような活動をしてもらいたいところはありますが・・・。


